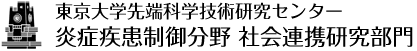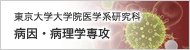研究内容
基本的には我々の研究は、確固とした分子生物学を土台とし、新しい技術や考えを積極的に取り入れながら、炎症・免疫系という複雑系をどう理解するか、という分野の先端的研究を目指しています。当然ながら、臨床医学とも深くかかわる分野であり、新しい治療法に路を開くことも視野に入れながら研究しています。以下に、現在進行中のプロジェクトについてもう少し具体的に述べます。プロジェクトの数が多いと思われるかも知れませんが、(学生を含めた)個々人の発想やプロジェクトへの想いを尊重する研究室の姿勢が理由のひとつに挙げられると思います。いずれも独創性のある最先端研究であることを自負しております。
(1) HMGB1による炎症・がんの調節機構の解析
 柳井らは、核酸による炎症・免疫応答の惹起の仕組みを解析するため、免疫原性を示す核酸をベイトにして網羅的な結合分子を検索した結果、核内でクロマチンに結合することで知られているHMGB1(及びそのファミリー)が同定されました。そこで更なる解析を進めたところ、HMGB1は細胞質内にも存在すること、そしてDNA, RNAを問わず、核酸による炎症・免疫応答の惹起にはHMGB1(及びそのファミリー)が普遍的に関与していることを明らかにしました(Nature,462, 99-103, 2009)。この知見を基に、HMGB1に強く結合する非免疫原性オリゴ核酸ISM ODNを合成し、このオリゴ核酸がHMGB1が関与すると思われる多くの疾患モデルにて強い抑制効果を発揮することを見いだしました(Proc Natl Acad Sci U S A.,108,11542-7, 2011). 現在、製薬会社と共同で開発研究を行なっています。 また細胞がある刺激を受けると細胞外に放出されることも判明し、更にその放出に必要なHMGB1修飾のメカニズムも明らかになりつつあります。更に、HMGB1遺伝子を組織特異的に欠損させるマウスの作製にも成功し、その機能解析も進んでいます(Proc Natl Acad Sci U S A.,110, 20699-704, 2013)。最近ではHMGB1ががんの転移に必須であることも明らかとなっており、今後の基礎・臨床研究が大きく進むことが期待されます。
柳井らは、核酸による炎症・免疫応答の惹起の仕組みを解析するため、免疫原性を示す核酸をベイトにして網羅的な結合分子を検索した結果、核内でクロマチンに結合することで知られているHMGB1(及びそのファミリー)が同定されました。そこで更なる解析を進めたところ、HMGB1は細胞質内にも存在すること、そしてDNA, RNAを問わず、核酸による炎症・免疫応答の惹起にはHMGB1(及びそのファミリー)が普遍的に関与していることを明らかにしました(Nature,462, 99-103, 2009)。この知見を基に、HMGB1に強く結合する非免疫原性オリゴ核酸ISM ODNを合成し、このオリゴ核酸がHMGB1が関与すると思われる多くの疾患モデルにて強い抑制効果を発揮することを見いだしました(Proc Natl Acad Sci U S A.,108,11542-7, 2011). 現在、製薬会社と共同で開発研究を行なっています。 また細胞がある刺激を受けると細胞外に放出されることも判明し、更にその放出に必要なHMGB1修飾のメカニズムも明らかになりつつあります。更に、HMGB1遺伝子を組織特異的に欠損させるマウスの作製にも成功し、その機能解析も進んでいます(Proc Natl Acad Sci U S A.,110, 20699-704, 2013)。最近ではHMGB1ががんの転移に必須であることも明らかとなっており、今後の基礎・臨床研究が大きく進むことが期待されます。
(2)細胞が放出する炎症・免疫制御分子の同定と解析
細胞が死を迎える際には核酸やタンパク質が放出され、炎症反応を引き起こすことが知られています。これらの分子はダメージ関連分子パターン(damage associated molecular patterns;DAMPs)と呼ばれ、炎症・免疫系を活性化し、自己免疫疾患や動脈硬化、がん、神経変性疾患など、炎症の関わる様々な病態に関わることが分かってきています。したがってDAMPsはさまざまな疾患に対する治療標的として注目を浴びていますが、このようなDAMPsの中に炎症・免疫反応を抑える分子が存在するかどうかは知られていませんでした。 特任研究員の半谷匠(はんがい・しょう)らは、細胞が死ぬと、プロスタグランジンE2(PGE2)が放出され炎症・免疫系を抑制することを見いだしました。実際、細胞が死を迎える際にPGE2の放出を抑えた場合、炎症・免疫応答が増強されることも明らかにしました。さらに、肝障害を患ったマウスにおいてもPGE2の産生を抑制するとその症状が悪化し、死んだ細胞による炎症反応が増強されることやがん細胞においてもPGE2の産生を抑制すると、抗腫瘍免疫応答が増強され、がん細胞の増殖が抑えられることもわかりました。 これまで、炎症・免疫系を引き起こす分子群として注目されてきたDAMPsの中には、実は、炎症・免疫反応を抑える働きがあることが明らかとなったことから、半谷、柳井らは、DAMPsをactivating DAMP(aDAMP)とinhibitory DAMP(iDAMP)に分類することを提唱しています(Proc Natl Acad Sci U S A.,113, 3844-9, 2016)。私たちの体内では正常時でも1秒あたり10万個の細胞が死んでおり、また炎症性疾患、がんなどの疾患においても大量の細胞死が起こります。今回の成果は個体の恒常性の維持やこれらの疾患の病態進展のメカニズムに新たな視点を提供し、新たな治療法開発に向けた分子基盤の確立につながっていくものと期待されます。 現在、半谷らはaDAMPの実体とその機能の解析を推進しています。
(3) IRFファミリーによる炎症・免疫制御機構の解析
 私たちのグループが発見した、IRF ファミリー転写因子についてそれらの遺伝子のいくつかを欠損したマウスを作製し、その解析を行うとともに、IRF因子群の機能を制御するシグナル伝達系の機構を解析してきました (Ann. Rev. Immunol., Vol. 19, 623-655, 2001;Nature Rev. Immunol., Vol. 6, 644-659, 2006)。既にIRF3, IRF7, IRF5がI型インターフェロン等の誘導に果たす役割を解明しました(Nature, Vol. 434, 243-249, 2005; Nature, Vol. 434, 772-777, 2005, Nature, Vol. 434,1035-1040, 2005)。注目されるのは、このメンバーを欠損したマウスでは、あるものはTh1型免疫応答、免疫応答の終息、樹状細胞の分化・機能などに異常があることが判明していることです(Nat Immunol., 9, 34-41, 2008)。また、IRF1ががん抑制因子であることは知られていますが、他のIRFとがん化抑制の研究もたいへん興味深いところです。実際、 IRF5が発がん抑制因子であること、細胞周期制御には関与せず、細胞死(アポトーシス)経路を活性化することが判明し、如何なるメカニズムが存在するのか、今後の興味深い課題です(Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol.101, 2416-2421, 2004;Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 105, 2556-2561, 2008; Oncoimmunology, 1, 1376-1386, 2012)。現在は、IRF3を組織・細胞特異的に欠損させたマウスの作製を終了し、解析を行なっています。
私たちのグループが発見した、IRF ファミリー転写因子についてそれらの遺伝子のいくつかを欠損したマウスを作製し、その解析を行うとともに、IRF因子群の機能を制御するシグナル伝達系の機構を解析してきました (Ann. Rev. Immunol., Vol. 19, 623-655, 2001;Nature Rev. Immunol., Vol. 6, 644-659, 2006)。既にIRF3, IRF7, IRF5がI型インターフェロン等の誘導に果たす役割を解明しました(Nature, Vol. 434, 243-249, 2005; Nature, Vol. 434, 772-777, 2005, Nature, Vol. 434,1035-1040, 2005)。注目されるのは、このメンバーを欠損したマウスでは、あるものはTh1型免疫応答、免疫応答の終息、樹状細胞の分化・機能などに異常があることが判明していることです(Nat Immunol., 9, 34-41, 2008)。また、IRF1ががん抑制因子であることは知られていますが、他のIRFとがん化抑制の研究もたいへん興味深いところです。実際、 IRF5が発がん抑制因子であること、細胞周期制御には関与せず、細胞死(アポトーシス)経路を活性化することが判明し、如何なるメカニズムが存在するのか、今後の興味深い課題です(Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol.101, 2416-2421, 2004;Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 105, 2556-2561, 2008; Oncoimmunology, 1, 1376-1386, 2012)。現在は、IRF3を組織・細胞特異的に欠損させたマウスの作製を終了し、解析を行なっています。
(4) 腸管の炎症・免疫系を制御するバクテリオファージに関する研究
 大学院生の一人(既に卒業して就職)が特任助教の根岸英雄(ねぎし・ひでお)らとともに、特定の腸内常在細菌に感染する新しいバクテリオファージを発見しました。その後、根岸と他の大学院生によって、このファージの感染が宿主細菌=の免疫原性を著しく高めることが判明し、この感染が潰瘍性大腸炎のマウスモデルにおいて病態の増悪に関っていることを示す予備的知見も得られました。一連の研究は特定のファージが宿主の炎症・免疫応答に影響を及ぼすこと示した初めての例であり、今後腸内細菌と宿主の相互作用の理解に新たなブレイクスルーをもたらすことが期待されます。実際にはファージ感染を受けた細菌による炎症・免疫系の活性化に関する詳細な分子機構の解明を行なうとともに、別種の細菌・ファージの組み合わせの探索および解析、ヒト常在ファージの探索および疾患との関わり等に関する研究を展開させることによって、新しい研究領域の開拓が期待されます。また、このようにして単離したファージは、応用的側面からも治療のツールとなりうる可能性を秘めていると考えられます。すなわち、ファージ感染によって細菌の免疫原性を変化させて炎症、免疫応答を制御することや、ファージ遺伝子を操作することによって特定の免疫調節因子をファージに産生させることにより宿主免疫応答を改変する、などにより疾患制御の分子基盤を確立できる可能性があります。実際、ファージ治療という言葉は古くから存在し、最近あらたな注目を浴びてはいるものの、基本的にはファージ感染による特定病原菌の排除、を目的としていることから、ファージの操作による炎症、免疫応答の制御、という私たちの発想とは異なったものです。
大学院生の一人(既に卒業して就職)が特任助教の根岸英雄(ねぎし・ひでお)らとともに、特定の腸内常在細菌に感染する新しいバクテリオファージを発見しました。その後、根岸と他の大学院生によって、このファージの感染が宿主細菌=の免疫原性を著しく高めることが判明し、この感染が潰瘍性大腸炎のマウスモデルにおいて病態の増悪に関っていることを示す予備的知見も得られました。一連の研究は特定のファージが宿主の炎症・免疫応答に影響を及ぼすこと示した初めての例であり、今後腸内細菌と宿主の相互作用の理解に新たなブレイクスルーをもたらすことが期待されます。実際にはファージ感染を受けた細菌による炎症・免疫系の活性化に関する詳細な分子機構の解明を行なうとともに、別種の細菌・ファージの組み合わせの探索および解析、ヒト常在ファージの探索および疾患との関わり等に関する研究を展開させることによって、新しい研究領域の開拓が期待されます。また、このようにして単離したファージは、応用的側面からも治療のツールとなりうる可能性を秘めていると考えられます。すなわち、ファージ感染によって細菌の免疫原性を変化させて炎症、免疫応答を制御することや、ファージ遺伝子を操作することによって特定の免疫調節因子をファージに産生させることにより宿主免疫応答を改変する、などにより疾患制御の分子基盤を確立できる可能性があります。実際、ファージ治療という言葉は古くから存在し、最近あらたな注目を浴びてはいるものの、基本的にはファージ感染による特定病原菌の排除、を目的としていることから、ファージの操作による炎症、免疫応答の制御、という私たちの発想とは異なったものです。
(5) 腸管免疫系の制御における臓器間連携機構の解析
消化管はユニークな免疫系を構築しており、そこでは免疫細胞がバランスよく保たれています。近年、腸管免疫系が腸内疾患のみに関らず、多くの他の疾患と関っているとの認識が広まっており、本研究分野は免疫学の重点課題ともいえる状況となっています。消化管免疫系の構築において,腸内フローラが重要なはたらきをしていることが徐々に明らかになってきていますが、腸内フローラを構成する個々の細菌種は,それぞれ異なる様式により消化管免疫系に影響をあたえることも知られています。一方、他の臓器が消化管免疫系や腸内フローラにどのような影響を及ぼしているか、については理解が進んでいません。研究室の大学院生の一人(既に卒業。就職)がその課題に取り組み、他臓器由来の免疫調節因子が腸管に運ばれ、腸内フローラの恒常性を維持するために重要である、という知見を得ました。その後、特任助教の西尾純子(にしお・じゅんこ)らによって、この因子が免疫細胞の恒常性維持にも重要であることが判明しています。このような「inter-organ regulation of the immune system」ともいえる新たな研究分野の展開は種々の疾患発症のメカニズムの解明にも繋がることが期待されます。
(6)自己免疫疾患の原因とその病態克服に向けた研究
免疫系が自己由来分子を認識し、自己の組織破壊に繋がる免疫応答を活性化することは長年知られてきましたが、自然免疫系においてはより最近になり、死細胞等によって放出される自己分子が自然免疫シグナルを活性化することが明らかにされています。このような応答によって惹起される炎症が多くの疾患に関与していることから、免疫応答を惹起するこのような自己由来分子に関する研究は世界的にも注目される分野となっています。しかしながらこのような自己由来成分の本態や機能、そして病態への関与については未知の点が多く残されています。特任助教の根岸英雄(ねぎし・ひでお)らが独自に取得したSLE及び関節リウマチの病態を強力に抑制する化合物KNを基に、その化合物の標的を検索したところ。低分子 RNAであることが判明しました。この自己由来分子であるRNAによる自然免疫系の活性化が如何に病態と関与するかを解明することで病因・病態の解明に繋がる可能性が高いと考えられます。そして、本研究は医薬品としての開発において極めて実現性が高い研究と考えられます。
(7) 自然免疫受容体によるがんの増殖・転移に関する研究
大学院生二人によって(既に卒業して就職)ナチュラルキラー(NK)細胞のがん細胞傷害活性がマクロファージや樹状細胞などの自然免疫細胞によって増強されること、および、その増強において自然免疫細胞に発現する自然免疫受容体の一つであるC型レクチン受容体Dectin-1が重要な役割を持つことを明らかにされました(Chiba et al., eLife, 3: e04177, 2014)。この発見は自然免疫受容体が、自己由来の「がん関連分子パターン(tumor-associated molecular pattern; TAMP)」をも認識すること、それががん免疫監視機構における重要なメカニズムを担うことを初めて明らかにしたものと考えられます。更に、特任研究員の木村好孝(きむら・よしたか)は柳井らと共同で、Dectin-2, MCLと呼ばれるファミリー分子ががん細胞の肝臓への転移を抑制することを見いだしました。そして、肝臓のマクロファージであるクッパー細胞(Kupffer cell)で発現しているこれらの受容体ががん細胞を認識して貪食する、という仕組みも明らかになりました(Proc Natl Acad Sci U S A, 113,14097-14102, 2016)。がんに対する自然免疫応答における本受容体ファミリー及びその作用機序に関する全貌解明が期待されます。
(8) 卒業生、OB/OGの進路につきまして
当講座は「お互いに学び合い、お互いを尊重する」ことを基本とし、出来るだけ個性豊かな研究者として最先端の研究を遂行できるよう、またプロモーションされるよう、努力しています。「当講座出身の先輩として、東大医学部時代(20年間)からは10名が既に大学の教授として活躍しています(慶應義塾大学、信州大学、千葉大学、東北大学、東京大学、名古屋市立大学、日本医科大学、北海道大学、横浜市立大学)、また、国内の各大学や研究機関において准教授、講師、助教(あるいは相当の職位)としてアカデミアのキャリアを歩んでいる卒業生も多数います。海外のラボへも大勢が留学しています。一方、企業就職を志望する人たちにも、希望に沿った進路に進めるよう協力しています。実際、製薬企業等(武田薬品工業、アステラス製薬、中外製薬、大日本住友製薬など)で活躍しています。