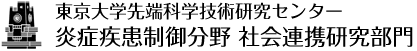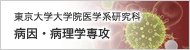免疫学研究の潮流
- 歴史的展開(概観)
- 抗体の発見とその遺伝子再編成
- Tリンパ球による抗原認識機構
- リンパ球の分化活性化機構
- 免疫寛容の仕組み
- サイトカインをはじめとする免疫系交信分子群の研究
- 自然免疫と適応免疫を結ぶ新たな研究の展開
- 癌と免疫の研究
免疫学は歴史的には古くても、常に新しい学問として、生命科学・医学研究の先端を担う分野のひとつとして発展してきました。分子レベルでの解明が大きく進み、特に(リンパ球が関与する)適応免疫系の成立とその制御機構の解明が進みましたが、一方で今後に残された課題は多く、社会的にも大きく期待されている研究分野です。例えば、自然免疫系と適応免疫系の連携メカニズム、アレルギーや自己免疫疾患の発症機構、免疫記憶や免疫寛容の仕組み、抗原提示細胞の成熟・活性化の仕組み、新興感染症などに対するワクチンの開発、癌に対する免疫応答機構、免疫シグナル伝達ネットワークの解明などが挙げられるでしょう。現代免疫学がどの様にして発展してきたかを概観し、今後の方向性について以下に概略を述べます。
1. 歴史的展開(概観)
免疫の「疫」は悪疫の疫を意味する。従って免疫は悪疫または伝染病を免れることを意味すると共に、生体に侵入または生体内で発症した異物(非自己)の排除が免疫系の根幹をなしている。免疫の概念の起源は、古くその歴史を溯るものである。実際に10世紀には痘瘡(天然痘;smallpox)の臨床的記述がイスラムの医学者Rhazesによってなされており、「免疫現象」の臨床的記述、すなわち免疫の根幹である「二度なし現象」の記述がなされた最も早いもののひとつと考えられる。その後、アジア、アフリカ、ヨーロッパで経験に基づいた(smallpoxに対する)接種(inoculation)が行われていた。そして18世紀末E. Jennerが牛痘を人為的に接種(種痘)することによって痘瘡の発症を予防することに成功したことが医学としての免疫学の発端といえよう。その後19世紀末、L. Pasteurは免疫現象を科学的に一般化し、ニワトリコレラやブタコレラ、炭疸菌などの感染予防や狂犬病の予防などへと免疫の方法を拡大していった。彼の業績は実用的な感染症の予防法(vaccination)の開発に留まらず、免疫の本質が再感染に対する生体の防御反応であることを示したことで近代免疫学の出発点として位置付けられる。一方で、いわゆる細胞性免疫(cellular immunity)の概念がE.Metchnikoffによって生み出された。
2. 抗体の発見とその遺伝子再編成
1890 年の北里柴三郎とE. von Behringによる血清療法という画期的な発見によって、「抗原(antigen)」とそれを認識し排除する「抗体(antibody)」の概念が確立された。更に、K. Landsteinerによる血液型および人工抗原の一連の研究は、抗体の「特異性」並びに「多様性」を爾後の解決すべき重要課題として提示した。すなわち、彼の研究は(1)免疫系が自己をも攻撃しうること、(2)個体の持つ(抗原に対する)抗体のレパートリーは無限に近く、個々の抗体は病原体に出会う為にのみ体内に用意されているのではない、ことを見出した点で画期的といえよう。言い換えれば、「免疫系は如何にして自己と反応しないのだろうか?」、「抗体の多様性と特異性はどのようにして獲得されるのだろうか?」という根元的な問題を提示したと言える。この流れは一方でR. Porter, G. Edelmanらによる抗体分子の化学構造解明へと展開して行き、抗原抗体反応の化学的理解が進んだ。またもう一方では多様性の問題、即ち無数の異物に対してそれに対応する抗体が如何にして生産されるかというLandsteinerが提起した重要問題に対してはNiels Jerne, David Talmage, F.Macfarlane Burnetらが大きな貢献をした。 特に、Burnetの「クローン選択説」はその後の免疫学の進展における大きなフレームワークを構築したと言えよう。そして1970年代後半から始まる分子生物学の免疫学領域への浸透の過程で、抗体(抗原受容体)の多様性獲得機構が基本的には遺伝子の再編成によって担われていることが、利根川進をはじめ多くの研究者によって解明されて行った。加えて、出来上がった抗体遺伝子にさらに体細胞突然変異(somatic mutation)が加えられることも示された。1989年にはこの遺伝子再編成を媒介する、RAG1/RAG2遺伝子の発見がD. Shatz,D. Baltimoreらによってなされ、1998年にはM. Gellert, D. ShatzらによってRAG1/RAG2 がトランスポゾン活性を持つという画期的な発見がなされた。一連の発見は適応免疫系の獲得・進化に対する新たな視点を提供したものとして特筆すべきであろう。
3. Tリンパ球による抗原認識機構
このような、抗体の関与する液性免疫(humoral immunity)に加えて、前述のMetchnikoffの研究に端を発する細胞性免疫(cellular immunity)の研究も並行して急速な展開をみせて来た。細胞性免疫研究において特筆すべきはB. Benacerraf, J.Dausset, H. McDevitt, G. Snellらによる組織適合性複合体(MHC)の発見とその免疫応答制御遺伝子としての同定である。臓器移植の成否を決定すると共に抗体産生の程度をも制御する遺伝子座として発見されたMHCのコードする分子(クラスIおよびII)が実はリンパ球のうちT細胞が認識出来るように抗原を「提示」する機能を持つことが、その後R. Zinkernagel, M. Bevan, E. Unanue, J. Kappler, P. Marrack,A. Towsendらによって解明されて行った。そしてP. Bjorkman, D. Willey, J.StromingerらによってMHC分子の立体構造が解析された結果、抗原ペプチドがMHC分子によって如何に提示されるのかに関する分子機構が解明された。 また、T細胞の抗原受容体遺伝子が1983-84にM. Davis, T. Mak, 利根川進らによって発見され、この遺伝子もRAG1/RAG2による遺伝子再編成を受けることが判明した。このT細胞の抗原認識研究の一連の流れは、より効果的なワクチンのデザインを考える上で極めて大きな情報をもたらし、医療分野への応用が期待されている。
4. リンパ球の分化活性化機構
リンパ球が他の造血系細胞と同一の幹細胞由来であるが、その分化の場である胸腺や骨髄の微小環境において支持細胞やサイトカインなどの影響を受けながら分化する機構に関しては詳細に渡る研究が進展し、抗原受容体遺伝子群の、制御された経時的発現の制御機構なども大筋は理解されるに至っている。また、最近ではリンパ節などの免疫系組織構築におけるリンパ球と他の細胞群との相互作用の重要性についても解析が大きく進んでいる。リンパ球活性化シグナル伝達の研究も大きな進展を遂げている。ここでは詳細は述べないが、この分野は免疫系にとどまらず、生命科学全体に於いても免疫学が先端を担って来た分野である。特筆すべきは、T細胞抗原受容体とMHC/peptideの相互作用に始まる、チロシンキナーゼの活性化とその下流分子群の活性化のカスケード・シグナルネットワークの機構とそのダイナミックな調節機構の解析であろう。同時にまだ「進化」を遂げつつある分野でもあり解明されるべき課題は多い。また、 Interleukin-2 (IL-2) 遺伝子の解析から得られた情報は、臓器移植時などに使用される種々の免疫抑制剤の作用機構の分子基盤をも提供した。
5. 免疫寛容の仕組み
「免疫寛容」(immunological torelance)、すなわち免疫系の根幹ともいえる自己と非自己の識別機構の研究は、Peter Medawarによる先駆的な移植片に対する寛容の研究に始まり、最近では主に遺伝子改変モデルマウスを用いた研究によって大きく進展している。いわゆる自己寛容の分子機構の解明は、自己免疫疾患の治療法を開発する上で必須の情報を与えると期待されているためこの分野の動向は大きな関心を持って注視されている。一連の研究により、Burnetが「クローン選択説」で提唱したように、自己反応性リンパ球(禁止クローン)は一次リンパ組織(胸腺、骨髄)において「負の選択」を受けることによって除去される機構が存在することが明らかとなった(中枢性寛容)。最近では、免疫系を負に制御するリンパ球サブセットとその分子機構の研究も進展している。実際、胸腺、骨髄での寛容獲得機構に加え、末梢での寛容の獲得と維持機構に関する研究は最近、大きな注目を浴びている分野である。なかでも坂口志文(京大)らが見いだした抑制性T細胞の研究は国際的に活発な研究が展開されている。
6. サイトカインをはじめとする免疫系交信分子群の研究
1950 年代より現在総称してサイトカインと呼ばれる可溶性免疫制御因子の存在が記述され始めた。通常、サイトカインの生産量は極めて微量であること、そして一つの細胞が同時に複数のサイトカインを生産することなどから、その研究は困難を極め、単一分子としての機能解析には程遠い状態であった。ちなみに初期の報告にある、リンパ球が産生する「増殖因子」とは今から考えれば類似の性状を持った多種のサイトカインの混在によるものであったといえよう。すなわち厳密に言えば、「インターロイキン」に代表されるように、単一分子として機能を示すサイトカインの遺伝子が果たして存在するのかさえ、当時は予断を許さない状況であった。したがって1970年代当時のサイトカイン研究の最重要課題は、サイトカイン分子の実体を解明し、単一分子としてのサイトカインが如何なる機能を持っているか、を明らかにすることであった。またこのような研究が、その後爆発的な進展をみせた、サイトカインによる細胞応答調節メカニズムの解明やサイトカインの臨床応用といった研究の展開にも重要であった。このように現象的記述に留まっていたこれらサイトカイン分子の研究は、インターフェロン(IFN)遺伝子の発見・確定と構造解明にはじまり、引き続きインターロイキン(IL)、腫瘍壊死因子(TNF) といった他のサイトカイン分子の研究へと広がり飛躍的な進展を遂げた。すなわち、特にこの分野は本邦の研究者が中心的な役割を果たし、世界をリードしてきた分野である。これらの構造解明は、急速に進展したDNA組換え技術と相俟って純粋なサイトカインの大量生産を可能にし、リンパ球増殖の分子基盤を研究する上で欠くべからざる道具を提供する事になった。このような背景のもと、サイトカインのシグナルを受け取る受容体もIL-2受容体を皮切りに多くの実体が分子生物学的に解明され、如何なるシグナルが受容体を介して免疫細胞内に伝達されるのかが急速に解明されており、免疫応答が可溶性調節因子のネットワークによって巧みに調節されている実態が明らかになりつつある。一方で、サイトカインは発がんとその制御にも深く関わっており、がん研究への貢献が大きいとともに、臨床応用可能な生体由来の免疫制御因子として近年臨床医学の分野でも注目を浴びている。実際IFNやIL-2などは直接そのものだけでなくそれらの機能を阻害する抗体も含めて、がん、ウイルス疾患あるいは自己免疫病の治療に用いられている。サイトカインの研究がもたらした、ともいえるもう一つの側面はTリンパ球の分化機構の研究である。すなわち、Tim Mosman らによってCD4陽性T細胞 (Th T cells)株にはサイトカインの発現プロファイルを異にする Th1型とTh2 型が存在することを見出した。このT細胞の分化経路は免疫応答の方向性を左右することが判明し、感染・癌に対する免疫応答の制御を理解する上で必須せあることから、制御機構に関する精力的な研究が展開している。最近ではTh1, Th2 に加え、Th17や Treg細胞の分化における各種サイトカインの役割とその作用メカニズムの研究も活発になっている。 サイトカインは可溶性の調節因子であるが、一方細胞表面に発現される分子もまた免疫担当細胞間の相互作用を調節することで免疫応答の制御に重要であることが認識されてきている。免疫系はその制御が破綻した場合には、例えばアレルギーや自己免疫疾患といった疾患が結果される。従って、システムとしての免疫系はきわめて精緻な制御がなされており、抗原受容体からのシグナルは必ずしも免疫応答を始める方向へ向かうとは限らない。このような免疫応答の方向性を決定するに与って最近益々その重要性が認識されるようになったのが、いわゆる細胞接着分子と呼ばれる一群の分子である。また一方でこれら細胞接着分子の幾つかは、リンパ球の循環、特定リンパ組織へのホーミングといった生体内での免疫系の空間的配置を決定するのみならず、炎症反応における免疫細胞のrecruitmentをも制御している事がわかってきた。また、ケモカインと呼ばれる一群のポリペプチドとその受容体は免疫系への関与は今では広く知られ、活発に研究されているところである。
7. 自然免疫と適応免疫を結ぶ新たな研究の展開
補体、インターフェロン、Natural Killer 細胞などが関与する自然免疫系は、従来からややもすれば適応検疫系との関連が明らかではなかったが、最近では実際に適応免疫系の誘導の根幹を担うことが分子レベルで研究されており、現在免疫学の最も注目される分野となっている。1996年にJ. Hoffmann らによってショウジョウバエ (Drosophila) の Toll 分子が抗菌(真菌)作用に必須であることが見出された。その後、1997年にはR. Medzhitov,C. Jenewayらが哺乳類(ヒト)において Toll-like receptor (TLR) の存在を見出し、現在では10種におよぶTLR が見出されている。すなわち、これらの分子は病原体由来分子を認識し、(樹状細胞などの)抗原提示細胞を活性化することによって適応免疫の誘導に重要な役割を果たしていることが判明しており、今後、有効なワクチン開発など多くの分野に貢献するものと考えられる。更に、米山光俊、藤田尚志ら(京大)によって見いだされた細胞質内RNA認識受容体(RIG-I, MDA5) や当研究室の高岡晃教(現;北大)、王志超、チェー・ミョンギョンらによって見いだされたDNA認識受容体(DAI)(Nature, Vol. 448, 501-506, 2007) などの研究も注目されているところである。
8. 癌と免疫の研究
20世紀初頭にP. Ehrlichによって提唱され、後にM. Burnetらによって展開してきた「免疫系によるがんの監視機構」の概念は、最近になって免疫不全マウスモデルを用いた研究などによってその証拠が多く提出されつつある。実際、免疫系の賦活化によるがん治療の研究も進展しつつあり、「がんの免疫療法」は次世代の新しいがん治療法として注目を浴びている。本来感染に対する防御機構として機能する免疫系が、がん細胞という「非自己」に対して応答するメカニズムの研究は、有効ながんの免疫療法を確立するための分子基盤を提供するであろう。がんに対する免疫担当細胞の活性化、エフェクター細胞によるがん細胞排除の機構については未知の点が多く残されている。がん細胞による免疫監視機構から回避、すなわち免疫寛容の獲得機構の解析も今後重要な課題となるであろう。一方では、がんの治療という観点から、抗体療法、ワクチン開発など実用化に向けた基礎研究の発展も期待されている。また、免疫・炎症のがん化への関与といった、発がん機構の解明という視点からの研究も重要な課題である。
このような歴史的背景を持つ免疫学は神経系等と並び、高次生命現象を理解する学問分野として急速に体系化が進んでおり、一時期言われた難解さは分子生物学的思考法の導入により生命科学の共通語を持って免疫学を語ることができるようになり、解消されつつある。また一方で医学諸分野での疾患研究の基礎としての免疫学の重要性が広く認識されるようになり、免疫学の基本を理解することは生化学、遺伝学等のそれとならんで欠くべからざるものとなっている。今後も免疫学は他の分野、分子生物学、遺伝学や細胞生物学といった基礎生物学のみならずアレルギー学、がん研究など臨床諸分野の進展と足並みをそろえて更に大きく進展する事は間違いない。今後、免疫系という精緻に構成された生体の防御機構の破綻がもたらす多くの免疫病の原因解明とその治療法の確立、あるいはがんの免疫療法といった医学への貢献がなされていくことが期待されている。